【書評】20歳の自分に受けさせたい文章講義
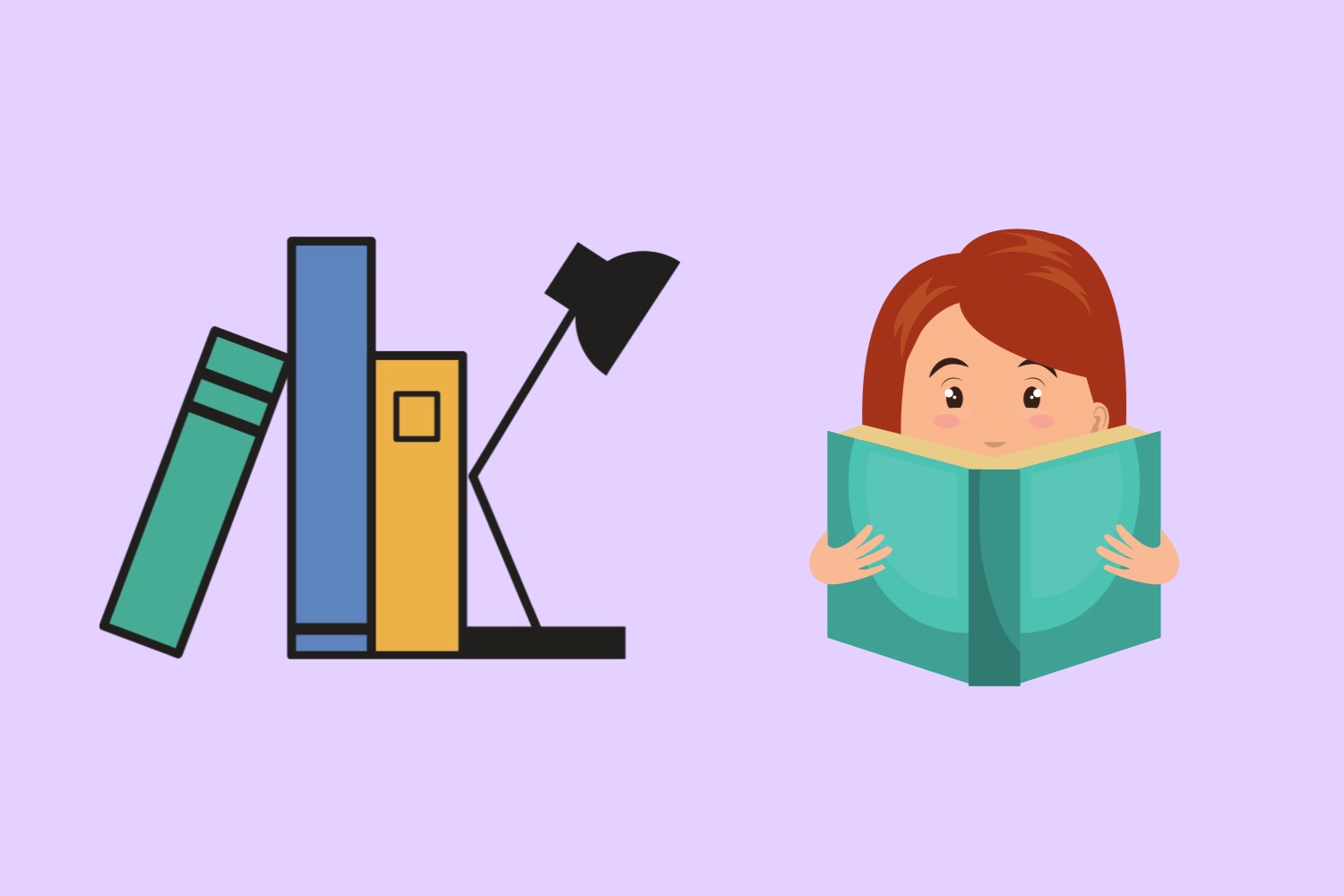
文章の書き方で悩む人「どのようにしたら読みやすい文章が書けるのだろうか?読者に読まれる文章にするためにはどうすればいいのだろうか?」
そんなお悩みの助けになる本がございます。
こんにちは、諌山(いさやま)です。
私もこの本をときどき読み返して、ブログの書き方の参考にしています。
この本の効用です
- リズムの良い文章の書き方がわかる
- 論理的で人を動かす文章の書き方がわかる
- 読者の設定がカンタンになる
- 文章を見直す方法がわかる
1.リズムの良い文章の書き方がわかる
文体とはリズムである。
リズムの悪い文章は端的に言えば「読みにくい文章」のことである。
リズムのカギは接続詞にある。
視覚的リズム
①句読点の打ち方
②改行のタイミング
③漢字とひらがなのバランス
著者は、文章の「リズム」を重視しています。
一般的によく言われる、センテンスの切り方や句読点の打ち方、改行のタイミングのようなテクニック論は、リズムの本質ではない、と切って捨てるほどです。
そして、文章のリズムは「論理展開」によって決まると主張しています。
さらに、文章の論理破綻をふせぐ方法の一つとして「接続詞」をもっと使うようにと言っています。
なるほどです。
私はどちらかと言えば、上記のテクニック論のほうを信じていたのですが、接続詞のことはけっこう見逃してましたね~。
さらに、著者は「論理展開」の重要性を踏まえた上で、読者は文章を目で読んでいることから「視覚的リズム」の大切さについても説いています。
視覚的リズムとは、文章を読んだときの気持ちよさのことでありまして、句読点の打ち方、改行のタイミング、漢字とひらがなのバランスによって生まれるものだと主張しています。
これはもちろん私も賛成です。
たしかに、字がみっちり詰まって四角いブロックにしか見えない文章って、読んでいてシンドイですから、私もブログを書くときに気をつけたいです。
2.論理的で人を動かす文章の書き方がわかる
さて、論理的な文章のマトリョーシカは、次の3層になっている。
①大マトリョーシカ 主張・・・・・・その文章を通じて訴えたい主張
②中マトリョーシカ 理由・・・・・・主張を訴える理由
③小マトリョーシカ 事実・・・・・・理由を補強する客観的事実
マトリョーシカとは、こんな感じ↓のロシアの人形です。

著者によると、論理的な文章というのはまず主張ありきと、熱く解説しています。
理由は主張の裏づけであり、事実は理由を補強する具体例でありまして、この三つが揃って読者に響く論理的な文章になると述べています。
他の書籍ではPREP(プレップ)法としてよく紹介されている手法ですが、この本ではマトリョーシカのような入れ子構造(しかも3層構造)にたとえながら、論理的な文章の作成法をくわしく語っています。
なお、当ブログでもこの3層の文章構造を使って書いていることが多いです。
私の場合は、読者に記事の全体像を一番先に読んでいただきたいので、だいたいの記事で主張を文章の最初に持ってきています。
3.読者の設定がカンタンになる
「10年前の自分」に語りかける
たったひとりの“あの人”に向けて書く
全ての読者は“素人”である。
著者は、たとえば「10年前の自分」に語りかけるように書くことで、必ず読み手に届く文章になると述べています。
昔の自分に向けて書くから、切実さがぜんぜん違うということですね。
「たったひとりの“あの人”に向けて書く」ことの意味は、少数派に向けて書いた方がエッジの効いた読者に伝わりやすい文章になるということです。
読者を広く取りすぎると、八方美人で、エッジが効いていない、ぼやけた内容になってしまい、何を書いているのかわかりにくくなる、ということだそうです。
しかも、その読者は「素人(シロウト)」だと思って書きなさい、専門用語や難解な言い回しをやめて、平易な書き方をしましょう、というものです。
私もなるべく平易な言葉で伝える努力はしているのですが、どうしても専門用語を書かなければいけないときは、その用語の解説を入れるようにしています。
4.文章を見直す方法がわかる
問題は「なにを書くか?」ではなく、「なにを書かないか?」なのだ。
推敲するにあたって最大の禁句となるのが「もったいない」である。
近くに家族や友人など気のおけない“読者”がいるのなら、一度読んでもらい率直な感想を聞かせてもらうといいだろう。
「なにを書かないか?」というのは、著者によると、書くべき元ネタ(素材・題材)はそこらへんに転がっているので、そもそも探す必要なんてなく、むしろ「なにを書かないか?」という意識を持たないといけないと断じてます。
なんでも書いてしまったら、内容が冗長になり、面白い文章にはならないということです。
全くそうですね。えへへ・・・・反省してます(汗)
さらに著者によると、推敲(すいこう)作業では、せっかく書いた文章だし「もったいない」から削らないなんてもってのほかだそうです。
そうですよね。
読者は、書き手の「もったいない」思いなんて知るはずもありません。
読者は、面白くて読みやすい文章かどうかを評価するだけなので、いらない文章はサクッと削りましょう、ということです。
でも、せっかく書いた文章を削るのツライのよね…(´ω`)
最後に、「家族や友人に一度読んでもらおう」というご提言ですが、じつは私はほとんどコレやってないので耳が非常にイタイです。。。。。近いうち家族にもブログ見てもらいます(大汗)
よろしければ本をお手に取ってご覧ください。





