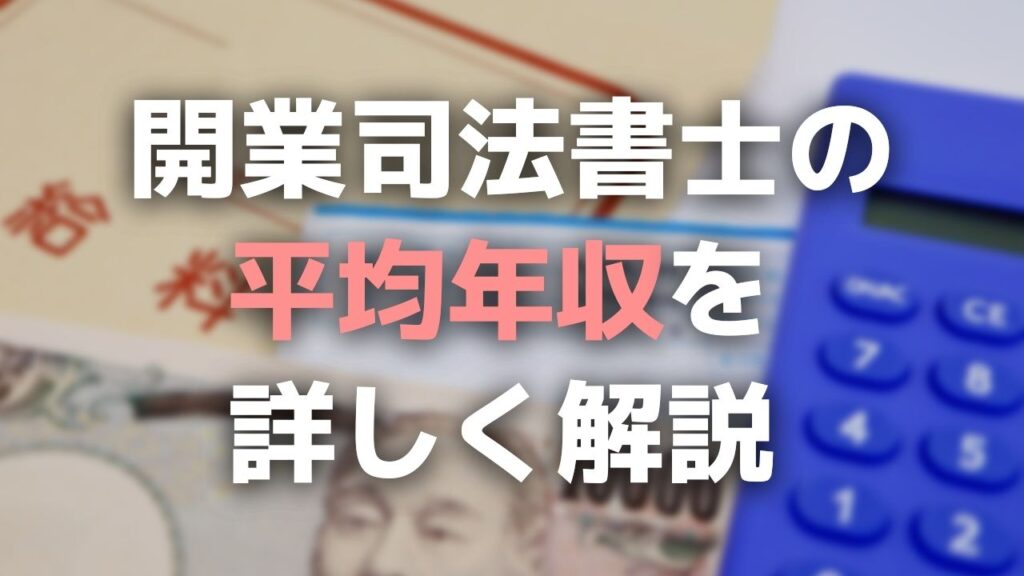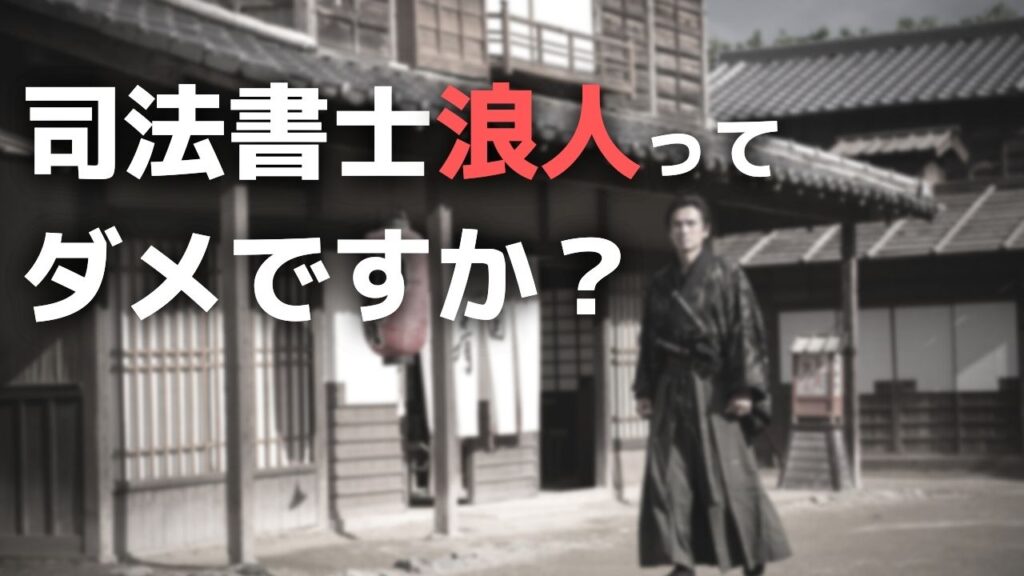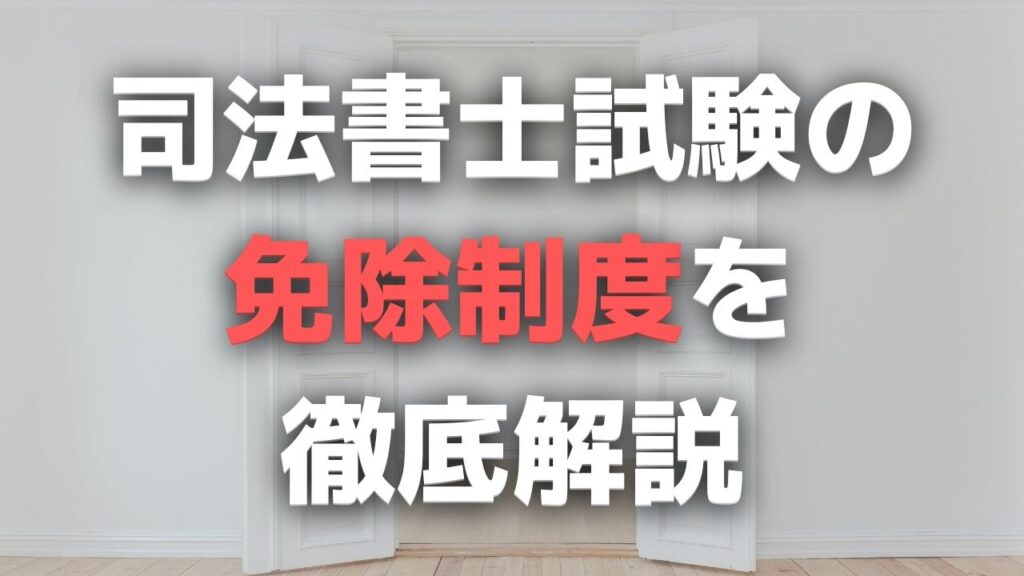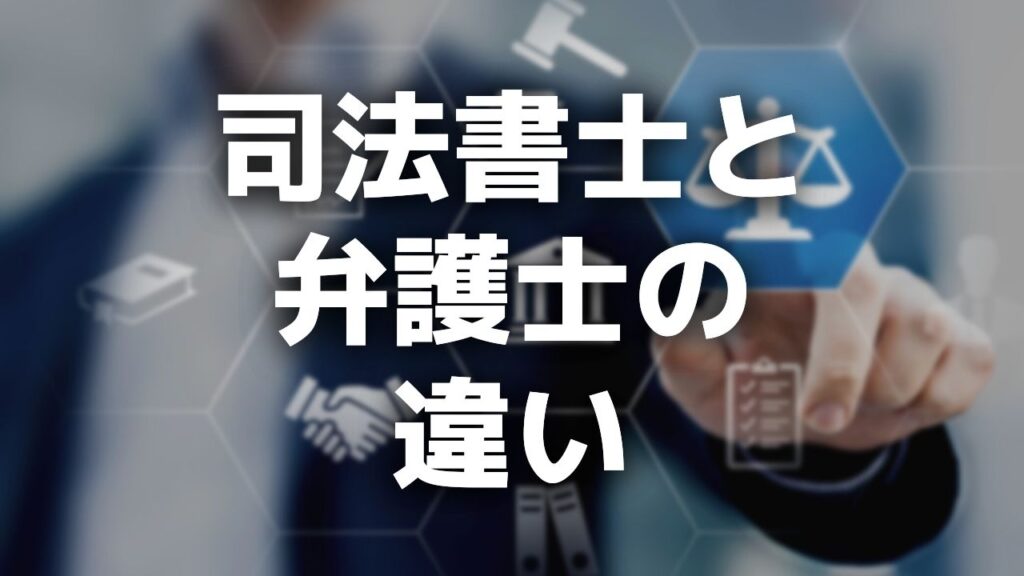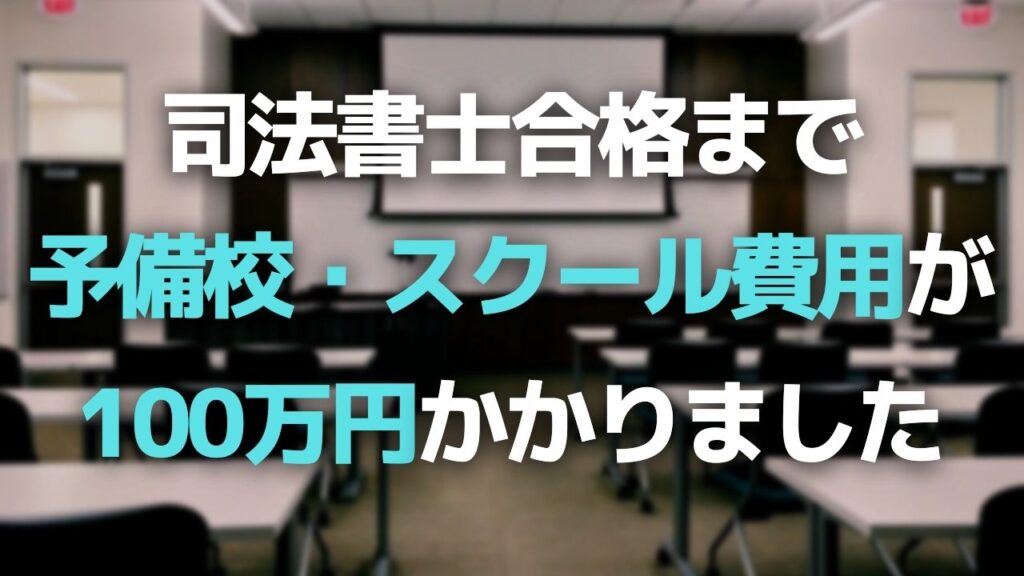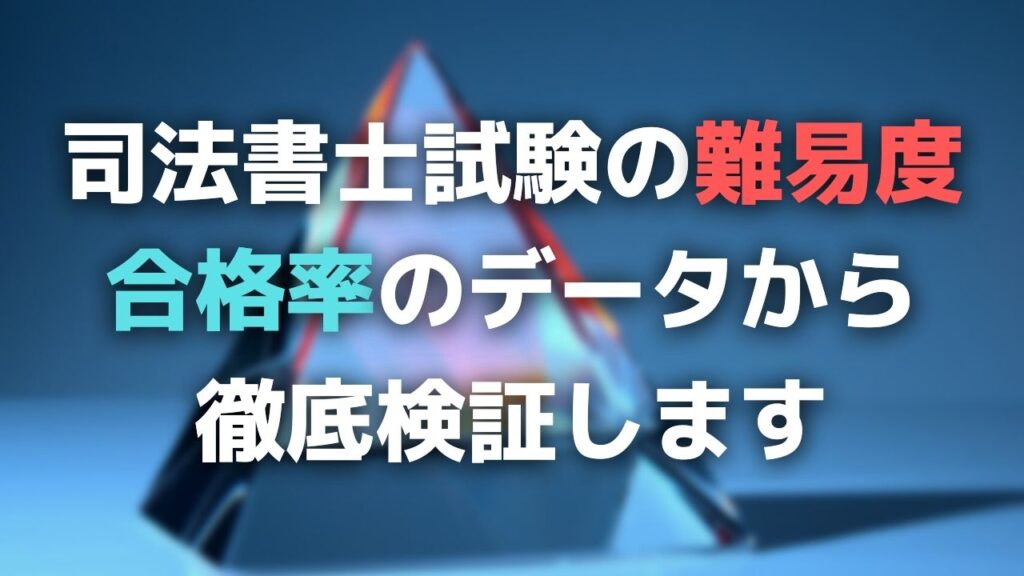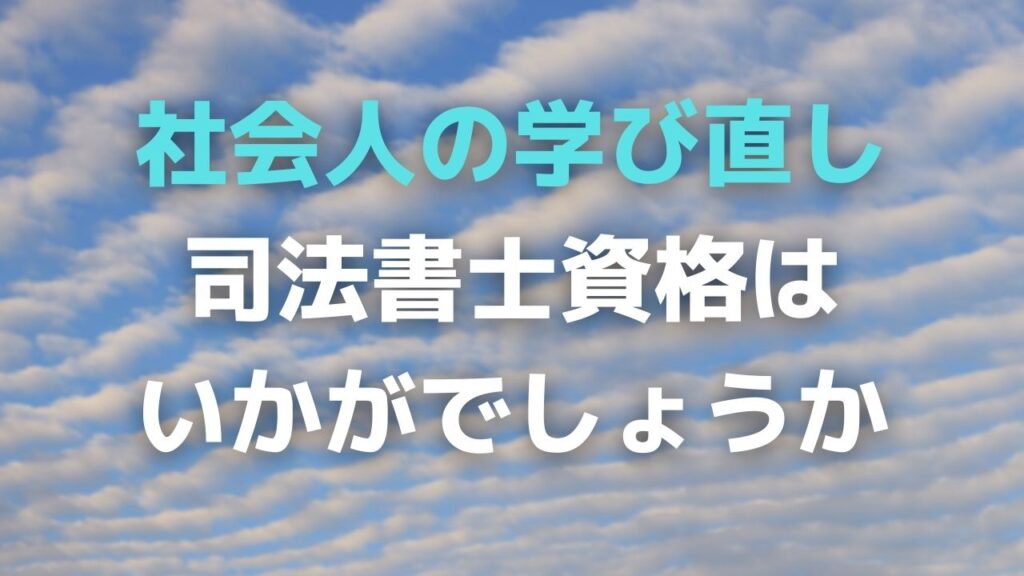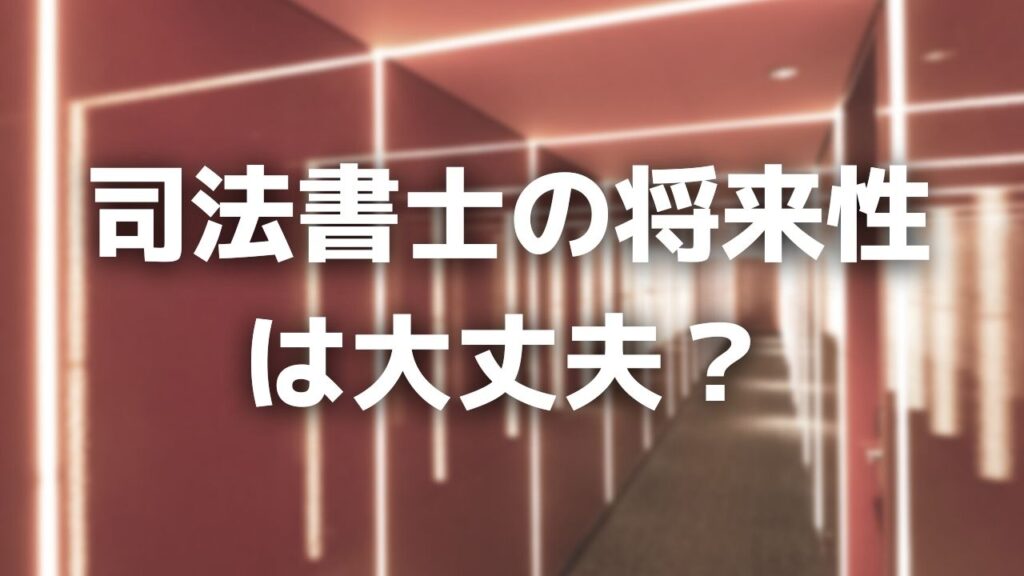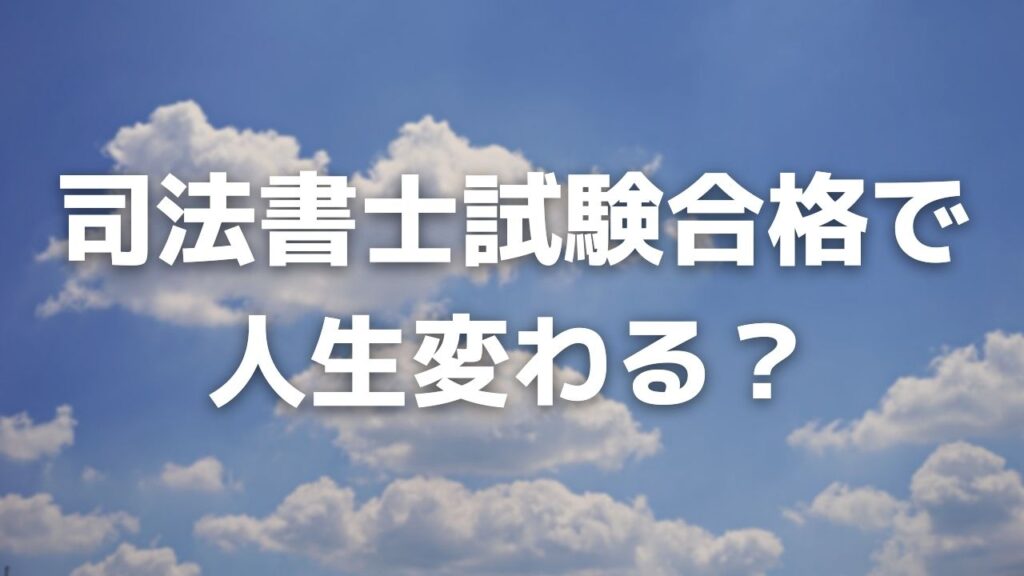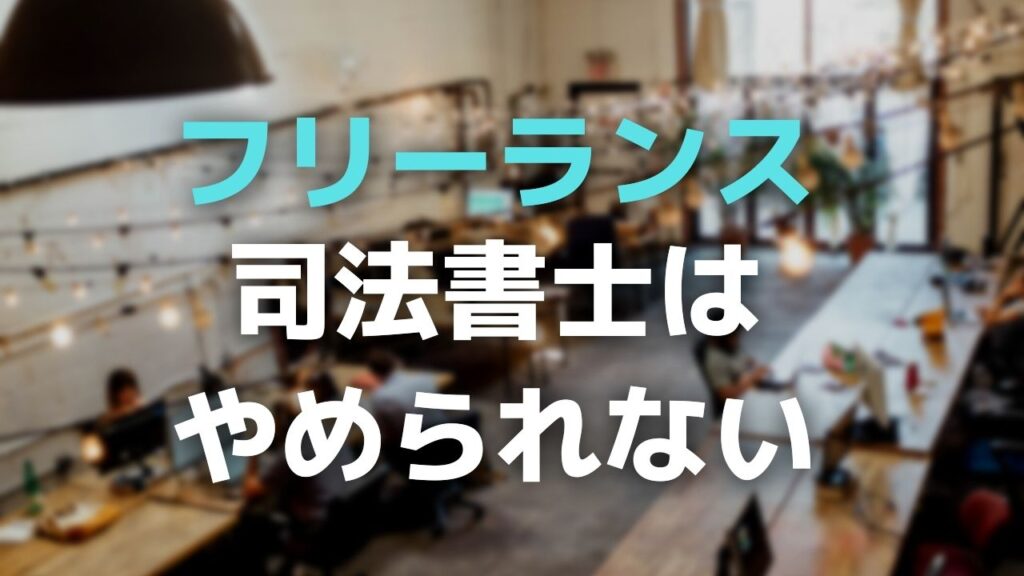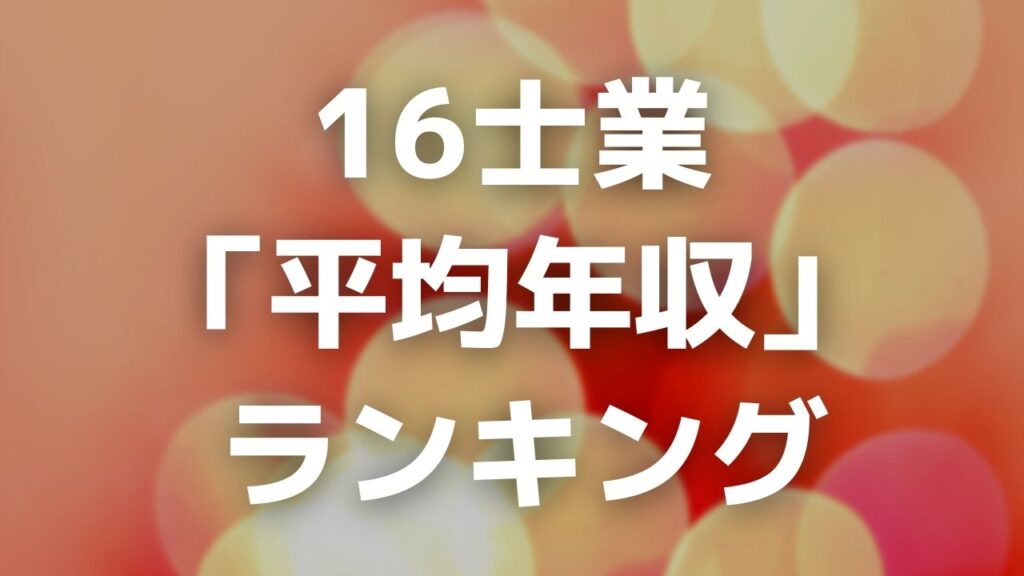司法書士と行政書士は違う資格です
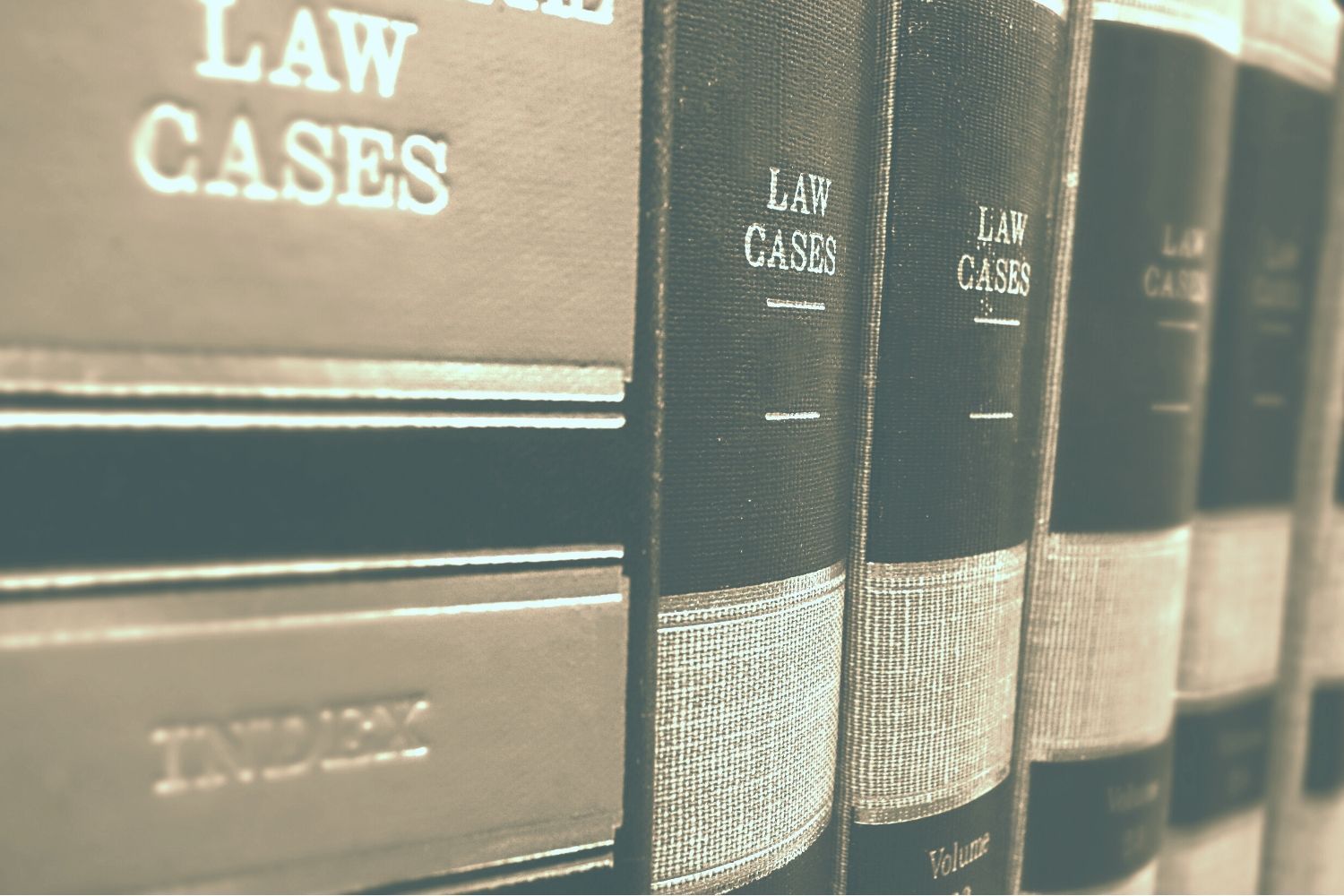
記事の概要
どうもこんにちは。司法書士の諌山です。
今回は、司法書士と行政書士の違いについて、わかりやすく解説したいと思います。
私は司法書士事務所を開業して10年目にようやく入りました。
司法書士として様々な業務をしていて、感じたこと考えたことをブログとして書いております。
この記事を読むメリット
役所に出す書類の作成を頼む時や、そのための相談は誰にすれば良いのか、という疑問がについて、少なくとも司法書士に頼めばいいのか、行政書士に頼めがいいのか、ほぼほぼ迷うことなく判断できるようになります。
ポイント
司法書士と行政書士というのは、業務範囲については司法書士や行政書士の事務所のHPなどを見ると色々書いてあるのですが、とりあえず細かい話は置いて置いて、取り扱う業務の違いについてお話しします。
司法書士も行政書士も、役所向けの書類を作って提出してくれる仕事であることは同じです。
ただし、司法書士と行政書士は、その資格によって書類の種類や提出先の役所が異なっています。
多少乱暴な区切りになりますが、その違いは次のとおりです。
- 司法書士→登記
- 1番は「不動産の登記」
- 2番は「会社・法人の登記」
- 行政書士→各種許認可の申請
その理由は次のとおりです
司法書士
司法書士というのは、法務局や裁判所に提出する書類の作成が主な業務です。
ですが、司法書士事務所のほとんどは、登記に特化しているところがものすごく多いです。
しかも、登記の中でも、不動産の登記に特化している事務所がこれまためちゃめちゃ多いという現状があります。
なぜそうなっているかといえば、不動産の登記は不動産会社との繋がりがあれば、次のようなメリットがあるからです。
- わりと定期的にお仕事が回ってくる。
- 報酬単価も割と高めで、安定した収入源になるからです
会社や法人の登記はどうなのかといえば、取り扱っている司法書士事務所は探せばもちろんいっぱいありますが、これをメインの業務としているところは少ないです。
取り扱っている事務所が少ないという意味ではなく、メインの収入源にしている事務所が少ないという意味です。
理由は不動産登記と逆で、不動産会社のように安定的に仕事の供給源が少ない上に、報酬単価がわりと低めだからです。
行政書士
行政書士は各種許認可業務だと述べましたが、その理由は次のとおりです。
行政書士の仕事は、行政書士法という法律を見ると、「官公署に提出する書類の作成」と書いてあります。
「官公署に提出する書類」といったらなんでもできるじゃないか、と一瞬思ってしますのですが、実はそうではありません。
これには、大きな例外がありまして、ほかの資格業が独占業務として行なっている業務は行政書士は取り扱うことはできません、という規定があります。
他の資格業の例:
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・司法書士など。
行政書士は、他の資格業が独占業務として行っている業務を扱えないということは、裁判所で弁護活動をしたり(弁護士)、企業の監査をしたり(公認会計士)、税務申告をしたり(税理士)、特許申請を出したり(弁理士)、登記申請を代理したり(司法書士)、ということは基本的にできないということになります。
そうなりますと、それらを除外したその他の業務、つまり各種の許認可業務の申請ということなります。
司法書士・行政書士業務の具体例について
司法書士と行政書士の仕事の違いについてご説明したところで、具体的な業務の内容を述べてみたいと思います。
司法書士の業務の具体例
司法書士の業務のうち主なものは次のとおりです。
- 不動産の権利の登記
※ただし、建物や土地の図面や構造を登記する人は土地家屋調査士です。 - 会社・法人の登記
- 裁判所に提出する書類作成
- 簡易裁判所で裁判の代理人をしてもらえる
※ただし、法務省が実施する簡裁代理認定考査に合格した司法書士に限ります。 - 民事信託(家族信託)の手続き
※自分の財産の管理を、家族や、信頼できる第三者に託して管理してもらうことです。
自分に何かあってもその財産の行方をあらかじめ決めることができる制度です。 - 遺産相続業務
※遺産相続業務のうち、不動産の相続登記は昔から司法書士がやってましたが、そこから業務を拡張して、相続が起こったときに、遺族に代って相続登記だけではなく預貯金の払い戻しや、株などの有価証券の名義書き換えなど、包括的に遺産相続のお手伝いをする業務を取り扱っている司法書士事務所も増えてきています。
司法書士の業務のうち主なものは上記のとおりですが、中には「裁判所」と聞いて、「あれっ、裁判所って弁護士の仕事じゃないの?」と思われる方もいるかもしれません。
裁判所に関する業務は、もちろん弁護士のお仕事です。
その一方で、司法書士は裁判所に提出する書類の作成業務はできます。
弁護士との違いは、弁護士は全ての裁判手続きについて依頼者の代理人として活動できます。
テレビドラマなんかイメージしてもらえばわかりやすいと思います
裁判所の法廷で依頼者の代わりに喋っている弁護士をイメージしてもらえばわかりやすいのではないかと思います。
ですが、司法書士の中でも、法務省の認定試験を受けて合格した司法書士は、簡易裁判所の裁判手続きについては依頼者の代理人として法廷で活動することができます。
一例として、今でもテレビやラジオでよく目や耳にするのが、過払金返還請求のコマーシャルですね。
あれは、司法書士事務所がやっているケースが多いです。
簡易裁判所で依頼者の代理人として活動できることなったからこそ、過払金返還請求の業務ができているんです。
行政書士の業務の具体例
ちょっと長くなりましたが、次に行政書士の業務の主な具体例を述べますと、次のとおりです。
- 飲食店営業許可の申請
- 酒類販売業免許の申請
- 古物商許可申請
- 建設業許可申請
- 旅行業免許申請
- 風俗営業許可申請
- 外国人の在留資格の申請(いわゆる在留ビザ)
- 陸運局で自動車の登録
- 農地転用の許可申請
- 会社の定款認証
※例えば株式会社を設立するときは、会社の基本規則を定めた「定款」という書類を作る必要があります。
しかも、この定款は公証役場という役場で、認証してもらう手続きが必要になります。
この定款認証手続きは行政書士事務所でも取り扱っています。
会社の定款認証と聞いて、「会社の登記は司法書士の仕事ってさっき言ってなかったっけ」と思った方もいるかもしれません。
司法書士は、会社の定款認証手続きと登記の申請ができます。
それに対して、行政書士は定款認証手続きまででしたら取り扱い可能です。
つまり、一部業務の範囲がかぶっているところがありますので、ややこしくなるのですが、
全部の手続きを一貫してできるのが司法書士、
定款認証手続きまではできるのが行政書士となっておりますので、
お客様のニーズに応じて事務所を使い分けてもらえばいいと思います。
まとめ
最後にまとめたいと思います。
多少乱暴な区切りになりますが、その違いは次のとおりです。
- 司法書士→登記
- 1番は「不動産の登記」
- 2番は「会社・法人の登記」
- 最近は、裁判業務・民事信託(家族信託)業務・遺産相続業務に力を入れている事務所もあります。
- 行政書士→各種許認可の申請
- ただし行政書士事務所によっては外国人のビザ申請、陸運局に対する自動車の登録の業務をしているところもあります。
そして、余談になりますが、この記事をご覧いただいている皆様に申し上げたいのですが、「司法書士と司法試験は全く違います。司法試験は弁護士になるための試験です。」
コレ結構勘違いされている方が多いので、述べさせていただきました。
ありがとうございました
というわけで、今回は、司法書士と行政書士は違う資格です、ということを解説いたしました。
最後まで記事をご覧いただきましてありがとうございました。
関連記事
司法書士の平均年収と本音を語ります【一攫千金ではなく地道に】
サラリーマンが副業として司法書士はできるのか?