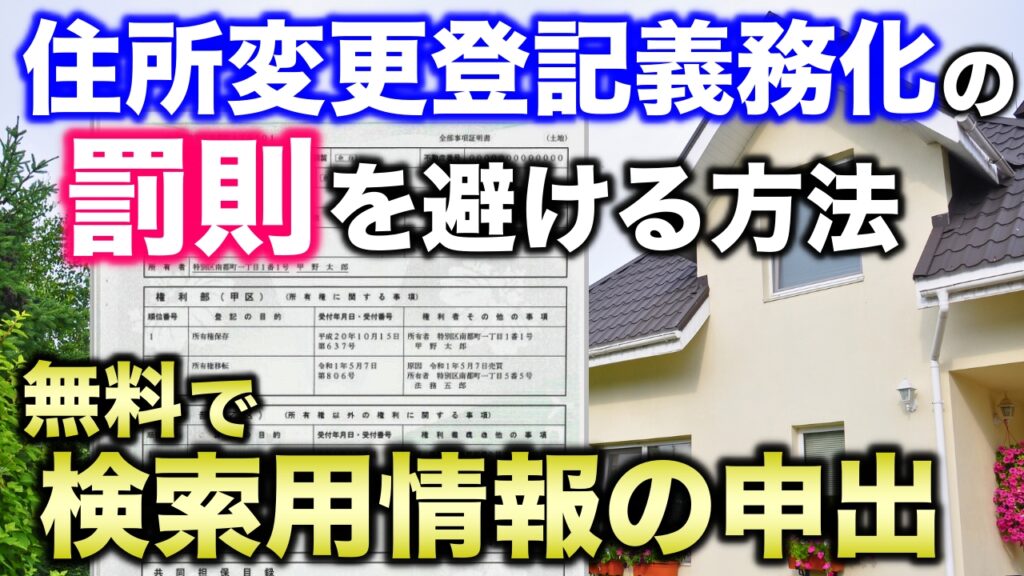相続登記の実費部分と司法書士の報酬を別々に分けて解説します

「相続登記の費用がいくらかかりそうなのかネットで調べたけど、よくわからない!」
「実費部分と専門家報酬の部分が、ごっちゃになって表示されているから、よくわからない!」
今回は、そんな疑問にお答えします。
相続登記の費用といっても、誰がやってもかならずかかる「実費」部分と、登記の専門家である司法書士に依頼したときにかかる「報酬」部分の2種類があります。
今回の記事は、
「実費部分の詳しい解説」、「実費総額のモデルケース」、「司法書士の報酬額の目安」の3部構成となっています。
相続登記の実費部分と報酬部分を、別々にわけてご覧いただける内容になっています。
この記事の筆者について
司法書士事務所を開業して、今年(2020年)で10年経ちました。
日々の業務をおこなっていて、感じたこと考えたことをブログに書いています。
この記事の概要
相続登記の実費部分の計算方法
相続登記には、登録免許税という税金のほかに、いろんな実費がかかります。戸籍謄本とか住民票といったものですね。
評価額が高くなる場合とか、相続人がたくさんになるとか、そんなときは実費も多めにかかることがあります。
筆者の実感ですが、戸籍謄本や住民票などの書類の取得費用は、ぜんぶで1万〜2万円くらいで済むことが多いように感じます。
その一方で、相続登記を申請するときに納める登録免許税は、不動産の評価額に大きく左右されますので、一言でお伝えすることは難しいです。ですが、一応の目安はこの記事を読んでいただければ、ほぼわかります。
そのほかにも、かかってしまう実費もありますので、項目別にご紹介します。
相続登記の実費一覧表
相続登記の実費としてかかるものは、主に次のとおりです。
| 対 象 | どんなもの | 実 費 (1通あたり) |
|---|---|---|
| 亡くなった人 | 戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍) → 出生から亡くなった時点まで | 750円ほど |
| 亡くなった人 | 住民票の除票(戸籍の附票) | 300円ほど |
| 相続人 | 現在の戸籍謄本 | 450円ほど |
| 相続人 | 住民票 | 300円ほど |
| 相続人 | 印鑑証明書 →遺産分割協議をするとき | 300円ほど |
| 登記で使う | 評価証明書(必要に応じて取得) | 300円ほど〜 |
| 登記の税金 | 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 登記の確認 | 登記事項証明書(登記簿謄本) | 600円ほど |
上記の実費のうち、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、評価証明書などの発行手数料は、お住まいの市区町村役場によって異なる場合があります。
登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)の金額は、どこの地域でも変わりありません。
戸籍謄本(亡くなった方)
亡くなった方について、「生まれた時から亡くなった時点までの戸籍謄本」を取得します。
つまり、現在の戸籍だけではなくて、それ以前の古い戸籍も取得することになります。
請求先は本籍がある市区町村の役所になります。
住民登録している住所と本籍は異なることがあります。もし、本籍がわからないときは「本籍の記載付きの住民票」を取得すると、本籍が書いてある住民票を取得できますので、そこで確認することができます。
現在の戸籍謄本は350円程度、古い戸籍謄本の取得は、1通750円程度かかります。
亡くなった方の戸籍謄本の通数は多くなります
亡くなった方の戸籍を全て取得すると、4〜5通くらいになることがあります。
どうして、戸籍の枚数が多くなるかと言いますと、そのわけは以下のとおりです。
結婚したときは新しい戸籍が作られて、そこに移動します。
→生まれたときは親の戸籍に入っていますが、結婚すると結婚相手とともに新しい戸籍が作られます。
生前に転籍している場合は移転先で新しい戸籍が作られます。
→結婚しているか関係なく、本籍地は別の場所に移すことができます。これを転籍と言います。同一市区町村だけではなく他の市区町村に転籍することもできます。
戸籍の改製があった場合は、改製後の戸籍だけではなくて、改製前の古い戸籍も取得する必要があります。
→時代によって戸籍がリニューアルされることもあります。戸籍の改製(かいせい)と言いますが、明治時代から平成までに数回の改製がおこなわれています。
したがって、亡くなった方の生まれてから亡くなる時点までの全部の戸籍を取得すると、だいたい4、5通くらいになることが多いです。
戸籍謄本(相続人)
法定相続人は全員、現在の戸籍謄本を取得する必要があります。
全員について、現在の戸籍謄本を取得してくださいね。
現在の戸籍謄本は1通450円程度です。
戸籍謄本は、本籍がある市区町村の役場で取得できます。もし、本籍がわからないときは、「本籍の記載付きの住民票」を取ってみると書いてあります。これで本籍を確認することができます。
住民票の除票・戸籍の附票(亡くなった方)
「住民票の除票(じょひょう)」は、亡くなった方の最後の住所地を特定するために取得します。
市区町村によって金額が異なる場合がありますが、1通300円程度になります。
これはどうして取得するのかと言えば、登記上の所有者の住所と、亡くなった方の住所が一致していれば、同一人物であることを証明できるからです。
もし、お引っ越しなどで、登記上の住所と一致しない場合は、住所が移転した経緯が全部わかる書類をそろえる必要があります。
その場合は、「戸籍の附票(ふひょう)」という書類を取得すると、複数回の住所移転の経緯が書いてあることがあります。
戸籍の附票とは、戸籍と一緒に役所に備え置かれている書類です。
戸籍には本籍は書いてありますが、実際に住んでいた住所は書いてありません。そのかわり戸籍の附票には、これまで住んでいた住所が時系列で記載されています。
本籍がある市区町村の役場に請求すると取得できます。
住民票(相続人)
相続人の住民票も取得します。
1通300円程度です。これは、住民登録している市区町村の役所に請求して取得できます。
印鑑証明書(相続人)
印鑑証明書は、遺産分割協議をする場合に取得が必要になるものです。
相続人全員で話し合って、遺産である不動産などを誰が引き継ぐのか決めることがよくあります。これを遺産分割協議と言いますが、その話し合いの結果を遺産分割協議書という書類にまとめます。
遺産分割協議書には、相続人全員が、市区町村に登録した個人の実印を押す必要があります。そして、その押した印鑑が実印であることを証明するために、印鑑証明書も取得することになります。
印鑑証明書は1通300円程度です。
評価証明書(相続登記で使う)
評価証明書(固定資産評価証明書とも言います)は、相続の対象となっている不動産の評価額を明らかにするために、必要に応じて取得します。
不動産の所在地にある市区町村役場で取得できます。(ただし、東京23区は都税事務所で取得します。)
手数料は地域の役場によってバラバラですが、不動産一か所あたり300円とか400円程度になることが多いです。
「課税明細書」でも評価額はわかります
評価証明書を取得しなくても、不動産の評価額がわかる場合があります。
「課税明細書」という書類をお持ちでしたら、その書類にも不動産の評価額が書いてあります。
課税明細書は、固定資産税・都市計画税の納税通知書と一緒に送られてくるものです。
課税明細書に不動産の評価額が書いてあれば、評価証明書のかわりに相続登記で使うことができます。
登録免許税(相続登記の税金)
登録免許税は、不動産の相続登記を法務局に申請するときに納める税金になります。
登記申請するとき、登録免許税の税額分の収入印紙を買って、登記申請書に貼り付けて納付します(書面申請の場合)。
登録免許税の金額は、固定資産評価額の0.4%の金額です。(税率は執筆時現在)
登記事項証明書(登記の確認)
登記事項証明書は、従来、土地とか建物の「登記簿謄本」と読んでいた書類のことです。
不動産の「面積」や「所有者」などの情報が書いてあります。
不動産登記の情報は、法務局のコンピューターにデータとして記録されていますので、そのデータを紙に打ち出したものを登記事項証明書と呼んでいるのです。
1通600円で、法務局という役所で発行してもらえます。(金額は執筆時現在)
登記事項証明書(登記簿謄本)いつ取れば良いのか?
登記事項証明書(登記簿謄本)はいつ取れば良いのかといえば、以下のとおりになります。
- 相続登記をする前に、現在の登記内容はどのようになっているのか確認したいときに取得します。
→手持ちの登記事項証明書が古いときは、新しいものを取ったほうが良いでしょうね。 - 相続登記をした後でしたら、登記が問題なく終わっていることを確認するために登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
→きちんと登記をしたのでしたら、その結果を書類として手元に残しておけば、あとで確認するときに手間がかかりません。登記をした後は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しておくことを強くおすすめします。
相続登記にかかる実費総額のモデルケース
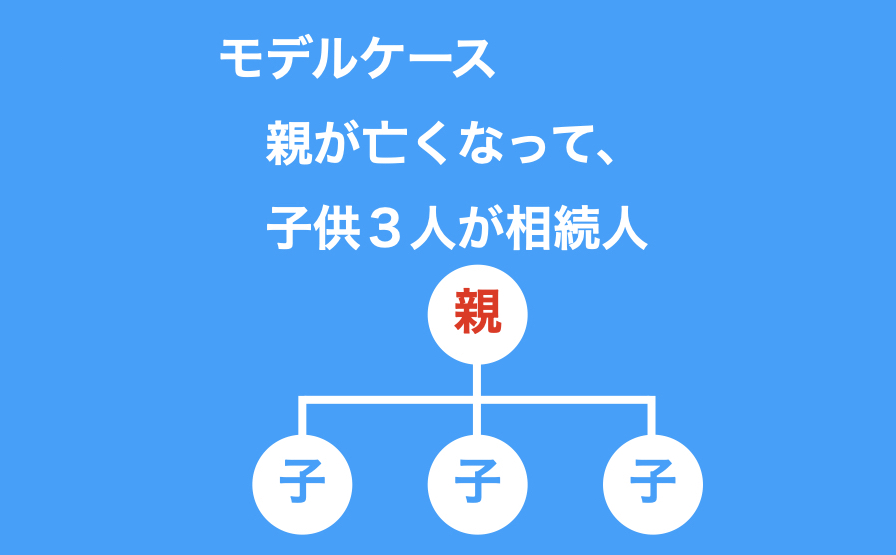
相続登記にかかる実費について色々解説しましたが、これだけだとわかりにくいですので、モデルケースを挙げてみたいと思います。
たとえば、親が亡くなって、子供3人が相続するケースです。
- 親の戸籍謄本を取得します。
→生まれた時から亡くなったときまでの戸籍謄本を取得したところ、仮に合計4通になったとすると、1通750円✖️4通=3000円です。 - 親について、住民票の除票を取得します。
→通常は1通取得すれば足りますので、300円✖️1通=300円です。 - 子供3人について、現在の戸籍謄本と住民票を取得します。
→戸籍謄本が1通450円、住民票が1通300円とすると、それぞれ3通ずつで、合計2250円になります。 - 登録免許税(相続登記を申請するときに法務局に納める税金)
→相続する不動産の固定資産評価額が仮に1000万円だとすると、税率は0.4%ですので4万円になります。 - 登記事項証明書を、相続登記が終わったあとに取得します。
→仮に不動産の数が土地1筆、建物1棟でしたら、合計2通取得しますので、1通600円✖️2通=1200円になります。
さてこのケースで費用を合計すると、
- 親の戸籍謄本代3000円
- 住民票の除票代300円
- 子供3人の戸籍謄本と住民票代で2250円
- 登録免許税代4万円
- 登記後に取得する登記事項証明書の代金1200円
合計で4万6750円ということになります。
あくまで、これは一つのモデルケースです。
不動産の数や評価額、相続人の数などによって、金額は高くなったり安くなったりしますので、その点はご了承いただきたいと思っています。
司法書士の報酬額の目安

さて、ここまで相続登記をするための実費部分の計算方法について述べてきましたが・・・
司法書士に相続登記の手続きを頼んだら、どれくらいの報酬がかかるのか?というお話しをこれからしたいと思います。
(自分で登記申請もするので、司法書士の報酬額はどうでもよい方は、ここでお別れです。ほかにも有益な記事を書いていますので、もうひとつご覧いただけますと嬉しいです。)
司法書士の報酬は自由化されていますので、依頼する事務所によって報酬の金額は異なってきます。
もちろん相場というか目安はありますので、ご紹介します。
日司連(日本司法書士会連合会)という司法書士の全国団体がありまして、司法書士が依頼者に請求する報酬額についてアンケートの結果を公表しています。
↓↓↓

2018年のアンケート結果になりますが、相続登記の報酬の平均は、おおよそ6万円から7万円程度となっています。
一応、以下のような条件がベースになっていますのでご留意ください。
- このアンケートのモデルケースは、土地1筆および建物1棟で、固定資産評価額が合計1000万円の場合です。
- 相続人は3人で、そのうち1人が、不動産を受け継いだ、という設定です。
- そのような不動産の所有名義を相続人に移す登記を、司法書士が依頼者に代わって手続きした場合の報酬の平均となっています。
相続登記の中では比較的難易度がやさしめのケースとも言えますので、この報酬額を鵜呑みにして、ご自分のケースにさっそく当てはめるのは避けたほうがいいです。
ただし、「司法書士の報酬の相場がどれくらいなのか?」、「だいたいの平均はこんなものだろうか?」、といった目安になるはずです。
まとめ
関連記事
遺産分割協議書の作り方入門・相続人がみんなで遺産の分け方を話し合う
相続登記の費用はいくらが多いのか?その疑問に答えます【実際のデータも初公開】
相続登記の登録免許税の免税措置について