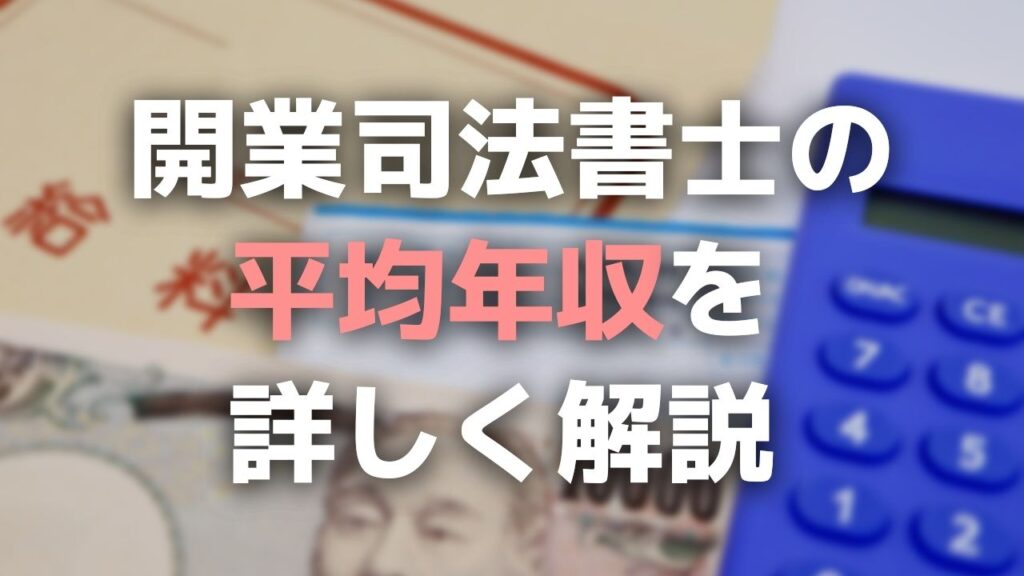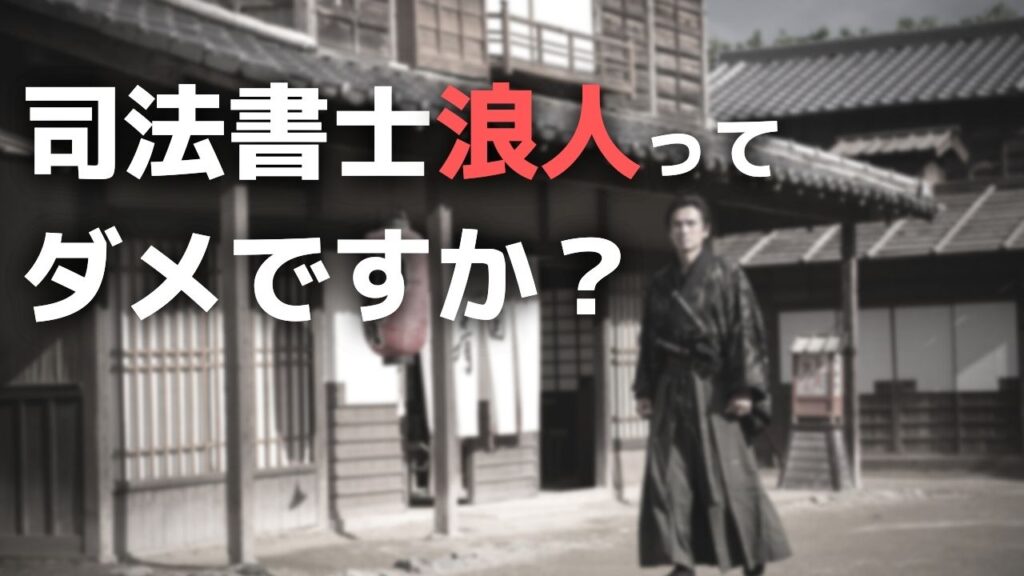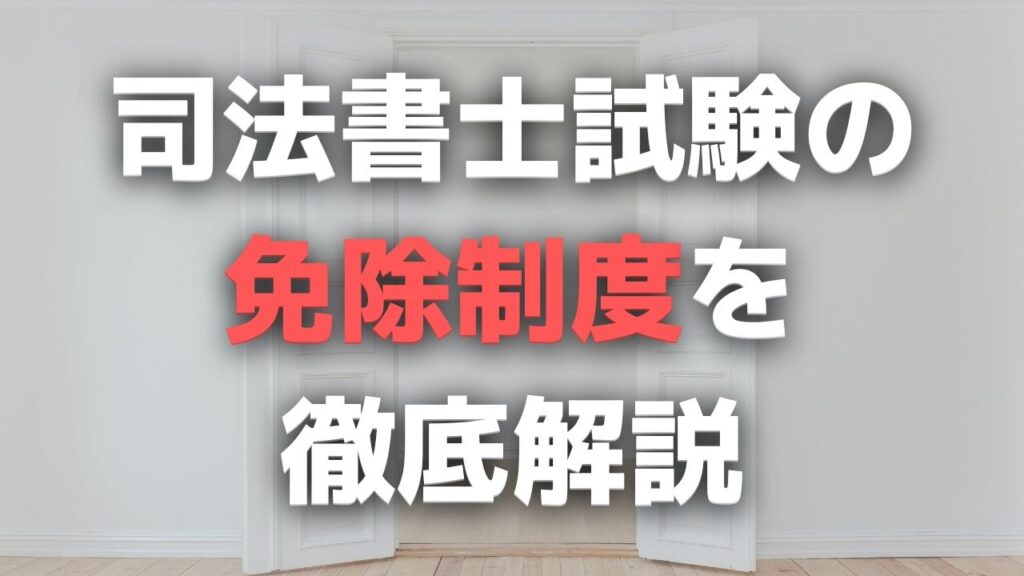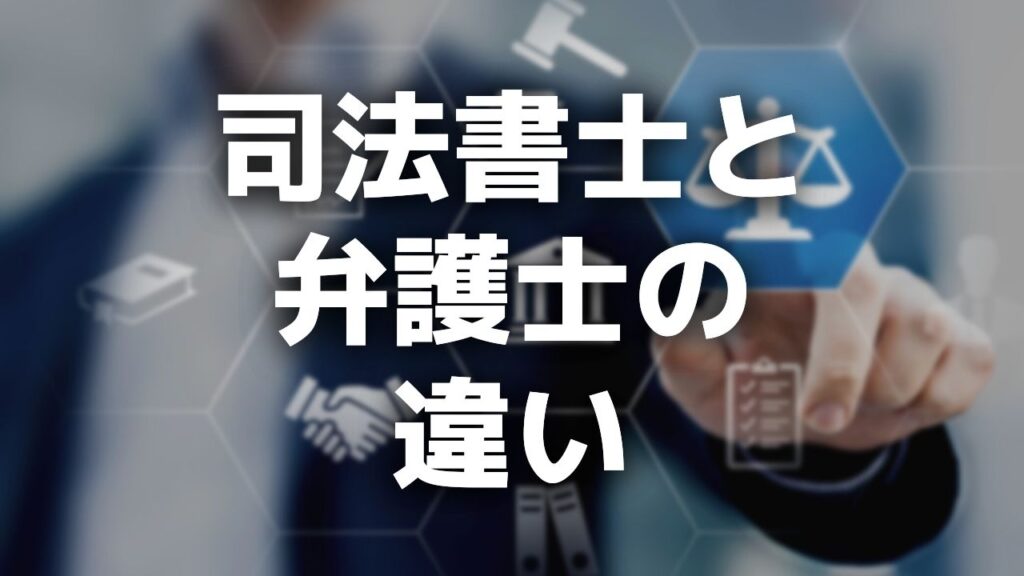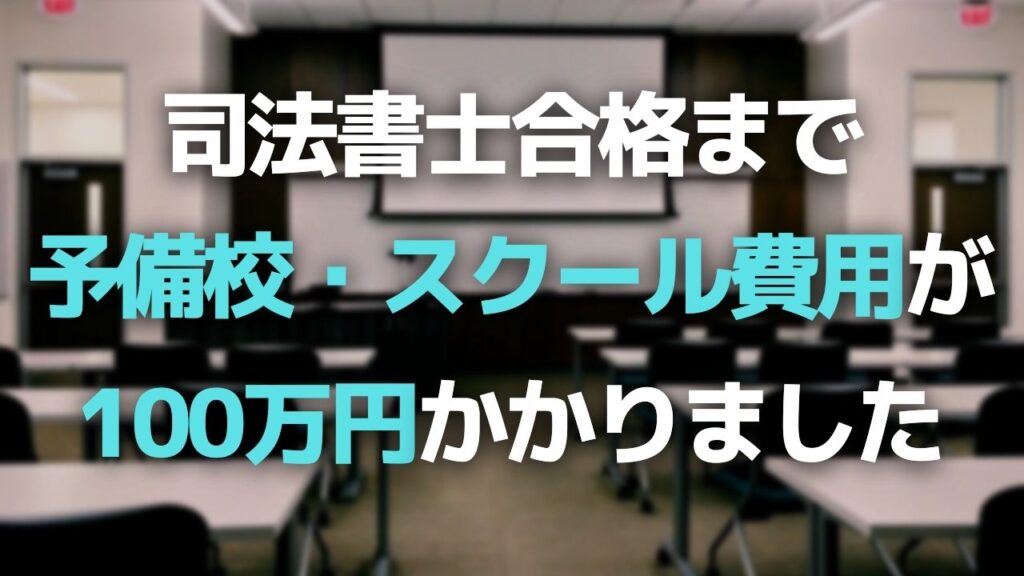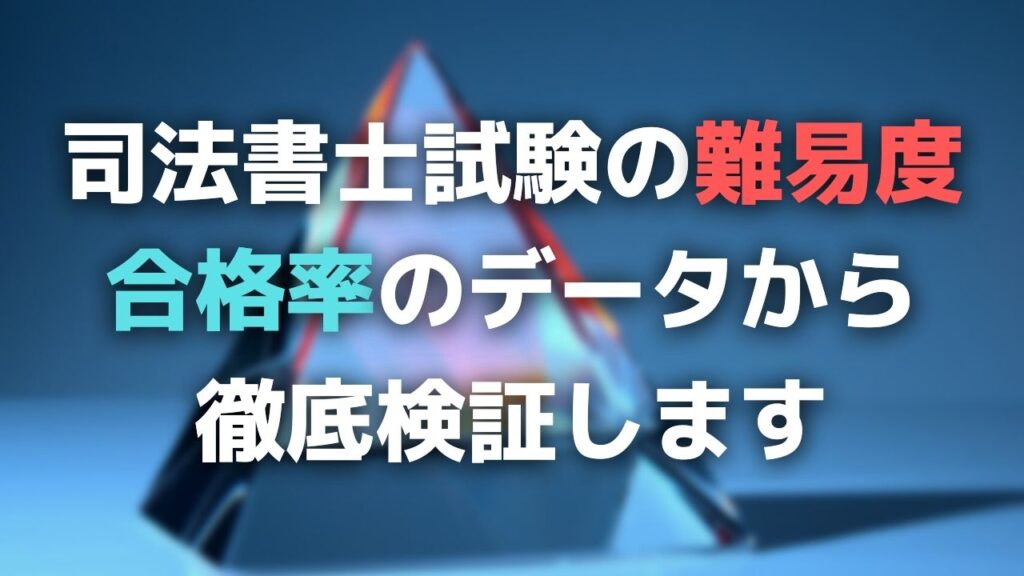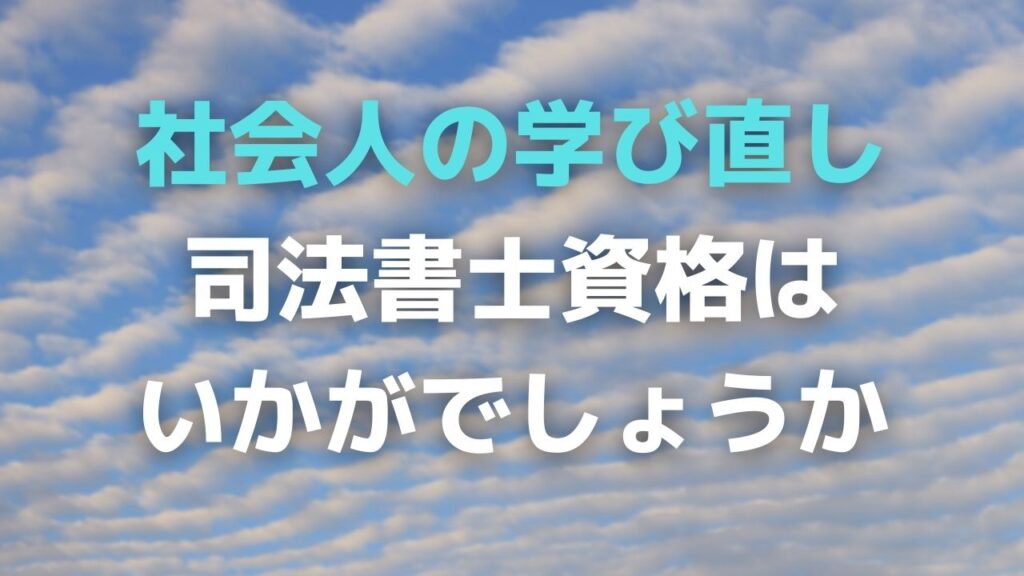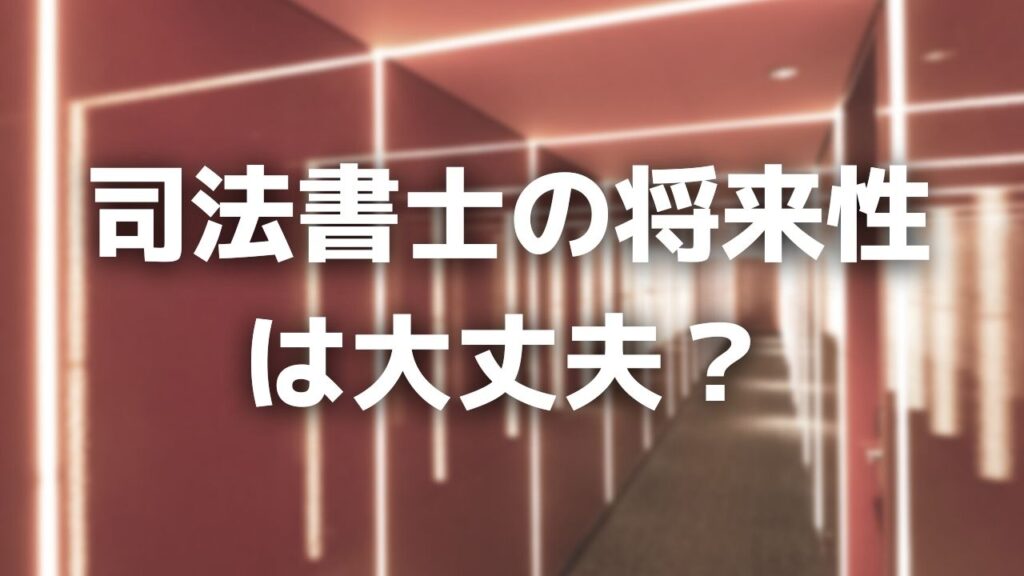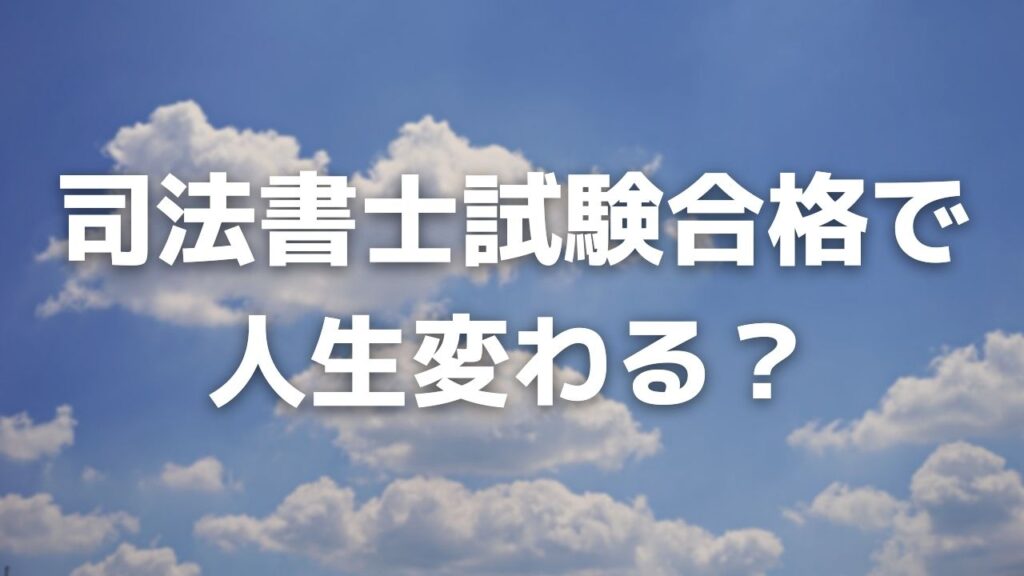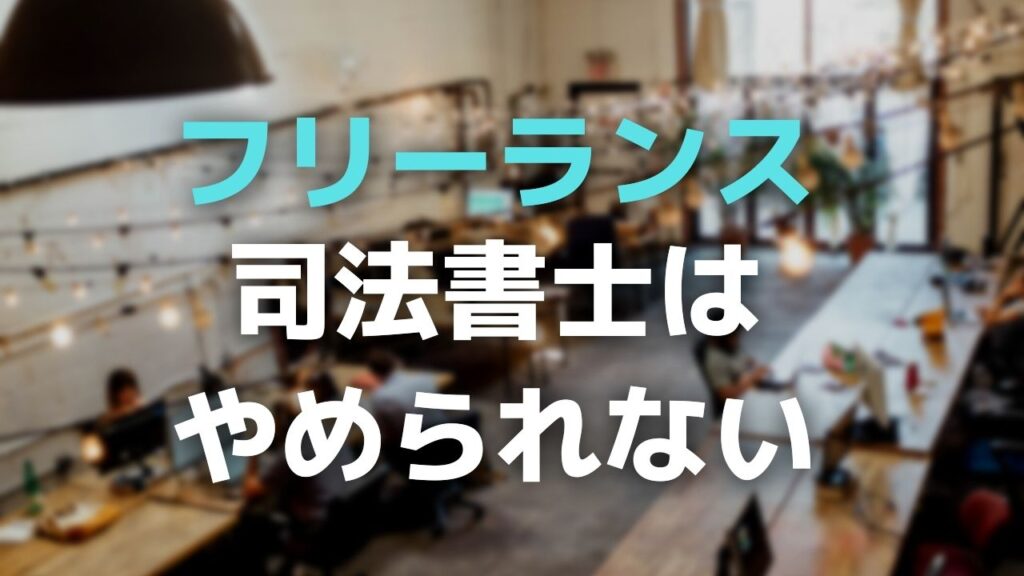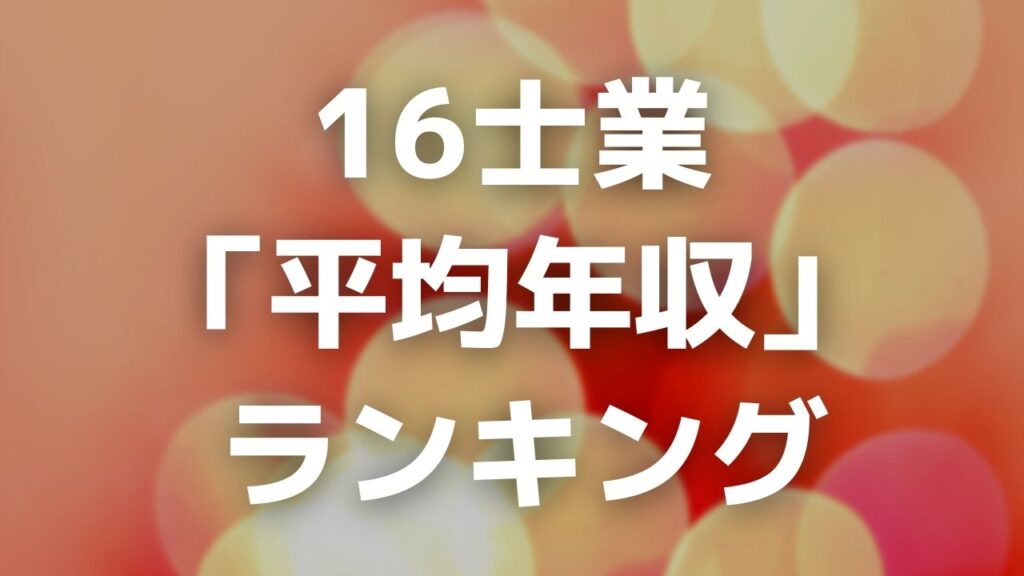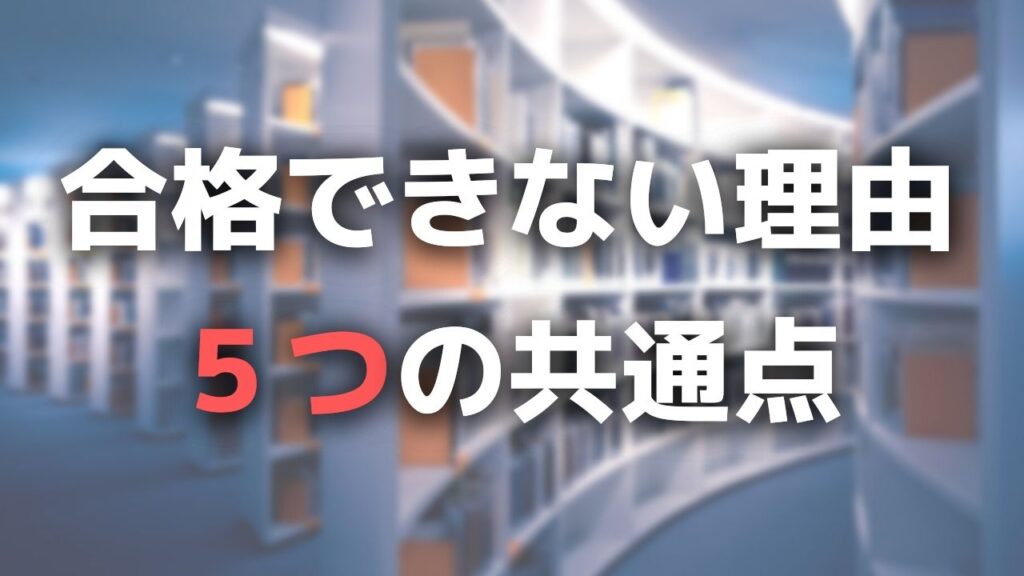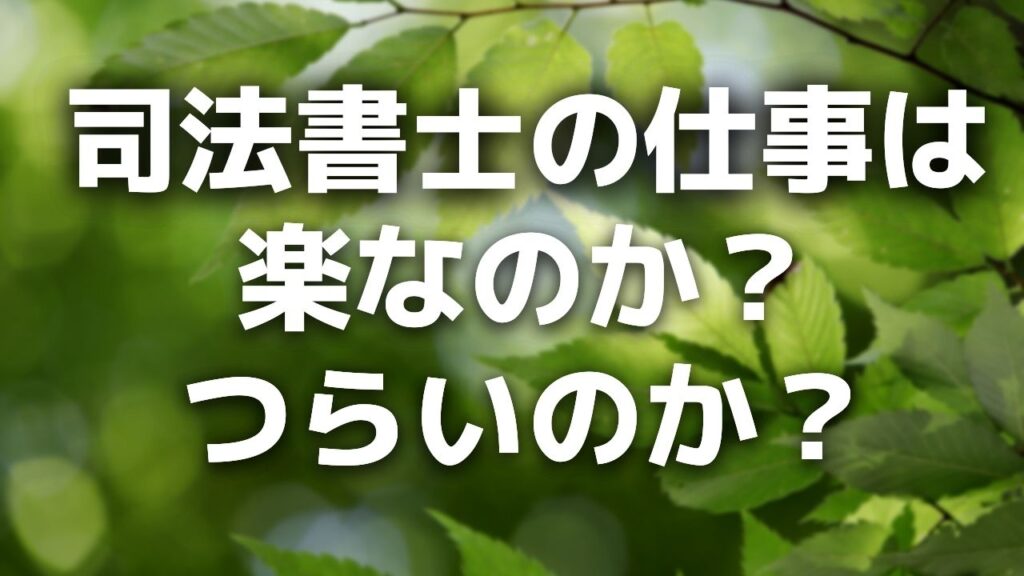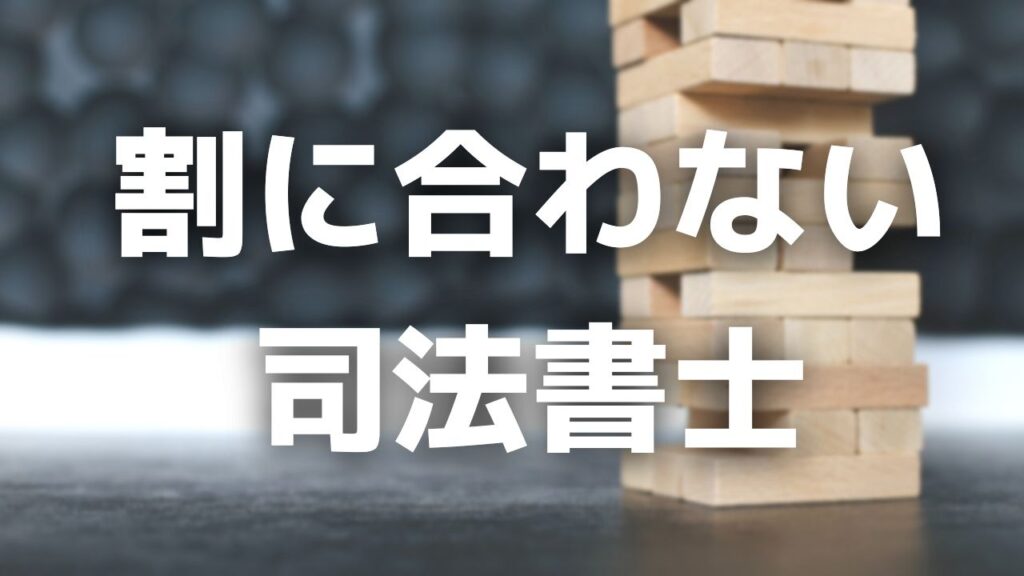司法書士は難関資格なのに割に合わないのか?コスパについて多角的に解説します
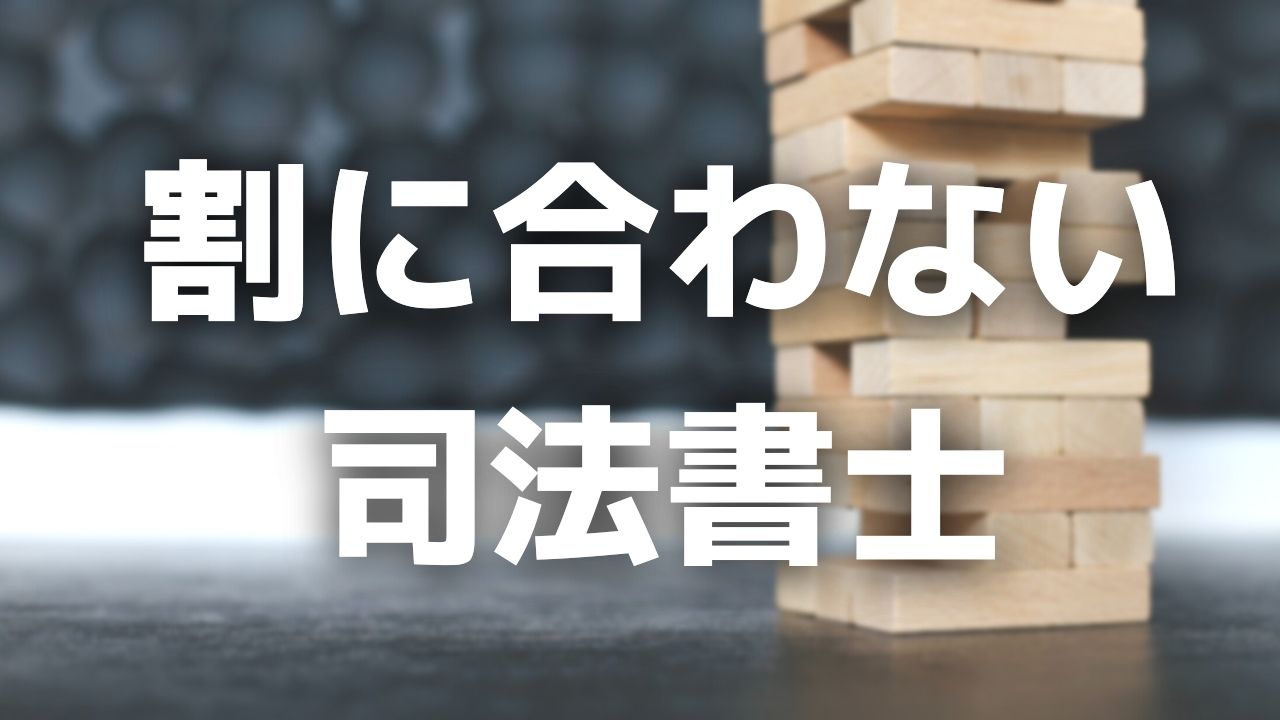
司法書士って合格率が3ー4%の難関試験です。
合格するためには3000時間の学習が必要だと言われています。
人によって合格までの学習時間は3000時間もかからなかったり、逆に多くかかったりすると思いますが、いずれにしてもそれなりの学習時間がかかることには違いありません。
それでは、こんな長時間学習してまで司法書士の資格を取るのってコスパがいいのか悪いのか、と疑問に思う人もいるかもしれません。
というわけで今回は、司法書士という資格を取っても割に合うのか合わないのか、解説してみたいと思います。
この記事の筆者
司法書士事務所を開業して今年で10年経ちました。
日々の業務をおこなっていて、感じたこと考えたことをブログで述べています。
この記事の概要
司法書士は割に合わないのか?
結論から言ってしまうと、お金だけを求めると割に合わないかもしれません。
というのも司法書士全体を見ると、稼いでいる人もいるけど、みんながみんな高収入というわけではないからです。
例をあげますと、司法書士の全国団体(日本司法書士会連合会)が公表している年収の統計資料があります。
2016年の司法書士実態調査によると、司法書士で年収1000万円以上の方は全体のおよそ17%とされています。
17%というと大したことないじゃないか?と思う人もいるかもしれません。
でも、日本人全体で1000万円以上の年収を得ている人はだいたい5%と言われてます。
これは国税庁の統計でそのような数字が出ています。
日本人全体と比べると、まだまだ司法書士の方が1000万円プレーヤーの割合は多いですね。
中間層の年収の割合はどうなっているのか?
こんなアッパークラスの話だけではなくて、中間層の年収のお話もしたいと思います。
先ほど引き合いに出した司法書士実態調査によると、1000万円以上がおよそ17%でした。
では、司法書士全体での「中間層の年収」の割合はどうなっているかといえば、
年収500万円から999万円までのゾーンに約33%が分布しています。
年収200万円から499万円までのゾーンは約30%でした。
司法書士の年収の分布(抜粋)
| 1000万円以上 | 約17% |
| 500〜999万円 | 約33% |
| 200〜499万円 | 約30% |
年収だけでは割に合わない人がいるかも
さて、司法書士の資格を頑張ってとっても割りが合うのか?という疑問についてですが、「年収だけでコスパ計算してしまうと、人によっては割に合わないと感じるでしょう。」という答えになります。
もちろん、年収という物差しは、国家資格を取るための重要なファクター(要因)になると思いますが、もう一つ、年収以外の部分でも割に合うかどうか、それについても考えてみたいと思います。
司法書士の廃業率のお話です。
いくら稼いだとしても、事業運営を長く続けることができなければ意味はありません。
廃業率の低さも考えよう【2%説】
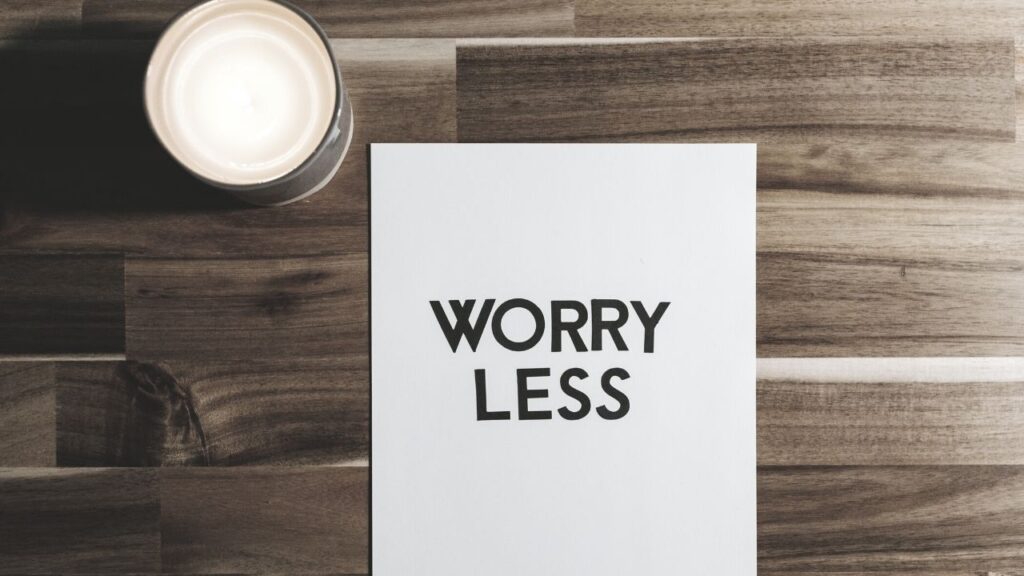
司法書士事務所はなかなか潰(つぶ)れない、というお話です。
司法書士の魅力として、廃業する事務所が少ないことが挙げられます。
司法書士事務所が潰れない理由としては、ランニングコストを安く済まそうと思えばできるからです。
- パソコンはそんなに高い性能のものでなくても構いません。
- プリンター・ファックス・スキャナーも商売道具としてそろえますが、最初のうちは家庭用でも大丈夫です。
- あとは、実務で使う参考書くらいです。
- 事務所は自宅でも全然構いません。事務員を雇うのでなければ、人件費は自分の生活費だけです。
モノに大金をかけなくても運営できてしまうから、司法書士の事務所は潰れにくいということを言いたいのですが、これだけだとちょっと感覚的なお話になってしまいますので、データ面のお話もしたいと思います。
司法書士の廃業率について推測する
ちなみに、司法書士の廃業率の公式なデータは見当たらなかったのですが、司法書士の全国団体が公表しているデータで参考になりそうなものがありました。
司法書士会員の毎年の登録取消者数のデータです。
司法書士の登録取消者数
| 年度 | 登録取消者数 | うち死亡者 |
|---|---|---|
| 2016 | 613人 | 117人 |
| 2017 | 569人 | 93人 |
| 2018 | 642人 | 132人 |
この資料によると、司法書士の登録を取り消している人は、毎年およそ600人います。
「登録取消者」というのは、司法書士としては廃業しました、という意味です。
このおよそ600人の中には、司法書士本人が亡くなった人数がおよそ100人含まれていますので、残りのおよそ500人が単純に司法書士をやめた人数ということになります。
司法書士全体の人数は全国でおよそ2万2000人ですので、単純に「司法書士をやめた人数」である500人はどれくらいの割合になるかと言えば、およそ2%になります。
もちろん、司法書士をやめてしまった人全員が、自分の事務所を持っていたわけではないと思います。
司法書士によっては、自分の事務所を廃業したけど司法書士の登録は取り消さずに、よその事務所に移って活動を続けている人もいるはずです。
そのようなことから、単純にこの2%という数字が廃業率になるわけではありません。
でも、司法書士を続けるのをやめた人の割合が、毎年およそ2%というのは少ないよなあ、と感じました。
他業界の廃業率との比較
司法書士をやめた人の割合(2%)が低いと感じる理由のお話です。
例えば、ラーメン屋さんってあなたが住んでいる街の中にもあると思います。
ラーメン屋さんは、一説によると開業してから1年以内の廃業率は50%くらいだと言われています。
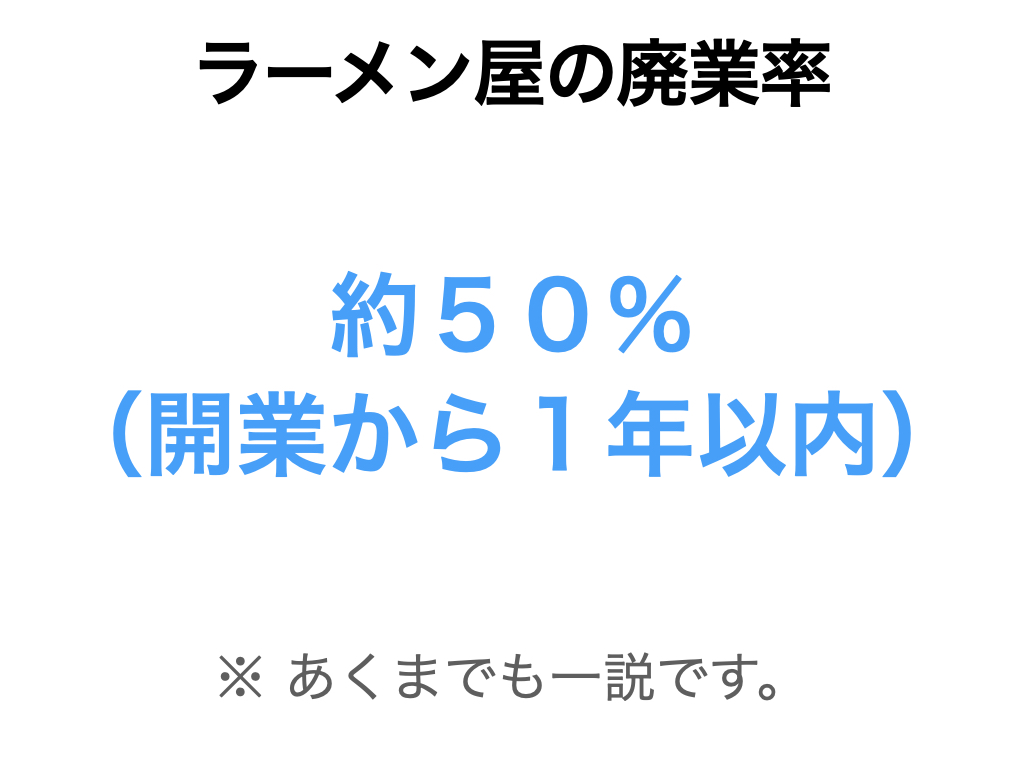
まあ、ラーメン屋さんの50%という数字は極端な例になりますが、これ以外にもう一つ例をあげます。
総務省と経済産業省による過去の調査によると、2016年の個人事業主の廃業率は業種にもよりますが、およそ6〜7%という数字が出ています。(総務省・経済産業省「平成 28 年経済センサス」)
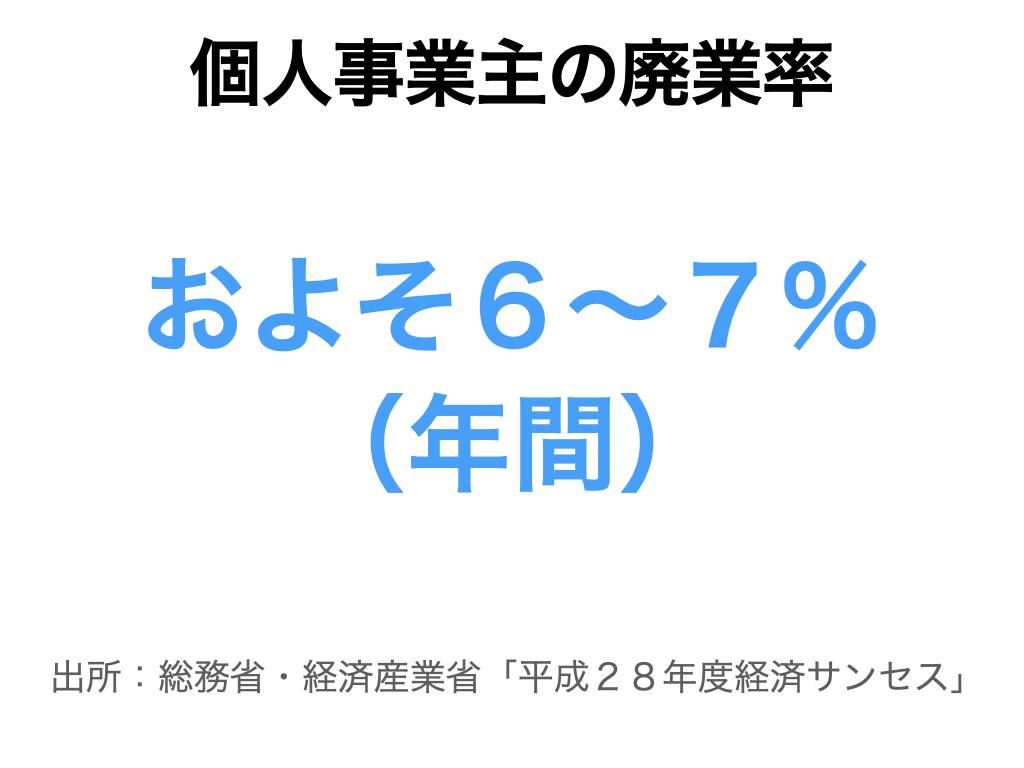
この6〜7%という個人事業主の廃業率と比べると、司法書士の登録をやめた人の割合が毎年およそ2%にとどまっていますので、よその業界より潰れる事務所は少ないのではないかと考えられます。
毎年の司法書士の受験者数が1万数千人いるのはなぜなのか?
というわけで、司法書士という資格を取っても割りが合うのか合わないのか、というお話の中で、司法書士の年収と廃業率について解説しました。
割に合うかどうかは「人それぞれ」と言ってしまうとそれまでですが、それでも不思議なことに、司法書士試験を受ける方って、毎年いっぱいいますよね。
一時期より受験者数は減少しているとはいえ、毎年1万数千人が受験しています。これはどうしてでしょうか?
法律系の資格でしたら、司法書士だけではなく弁護士という資格もあります。こちらの方が一般的にはネームバリューがありますし、年収も高いような気がします。
それでもどうして司法書士試験を受ける人はまだたくさんいるのでしょうか?
そのことについては次のトピックでお話ししたいと思います。
司法書士試験を受けるためのコストにも目を向ける

どうして司法書士を目指すのかというお話ですが、その答えは、受験資格とか学歴関係なく誰でも受験できる法律資格だからです。
司法書士試験は、高校や大学を出ていなくても、学歴関係なしで誰でも受験できます。
試験は毎年1回は行われていますので、毎年合格するためのチャンスが用意されています。
弁護士になるための司法試験との比較
ところで、司法書士と同じような法律系の資格で「弁護士」という資格があります。
弁護士といえば法律系の資格の最高峰です。裁判のプロですよね。
この弁護士と比べると、司法書士ができることは、主に登記申請の手続きや、裁判所に提出する書類作成などに限定されています。
もう一つ、司法書士の上乗せ資格として、法務大臣の認定を受けると、簡易裁判所で依頼者の代理人として活動することができるようになりますが、でもやっぱり簡易裁判所に限られてしまいます。
「だったら弁護士をとればいいじゃないか。」と思う人もいるかもしれませんが、そうすることが難しい人が世の中にはいっぱいます。
というのも、弁護士になるための試験として司法試験というものがありますが、受験するためには原則として、学歴と受験資格が必要になってきます。
司法試験を受験するためには学歴と受験資格が必要
ご存知の方もいると思いますが、司法試験を受験するためには、まず法科大学院という学校で最低でも2年間学ぶ必要があるのです。これが原則になっています。
しかも、その法科大学院に入学するためには、原則として大学を卒業していなければなりません。
つまり、弁護士になりたいと思って、司法試験を受験するためには、まず、大学を卒業していることと、さらに、法科大学院で最低でも2年以上学ぶことが必要になってきます。(原則)
もちろん法科大学院はボランティアでやっている教育機関ではありませんので、学費がかかります。
法科大学院に通うための学費が、いくらくらいかかるかといえば、安くても200ー300万円以上はかかります。
ということで、弁護士になるための司法試験を受験するには、金銭的・時間的なハードルが高いということがおわかりいただけると思います。
すでに社会に出て働いている方には、かなりハードルが高いと思います。
司法書士試験を受験するためのコスパはとても良い
司法書士試験はどうかといえば、受験するまでのコスパはものすごく良いです。
もう一度言いますと、司法書士試験には受験資格とか学歴は関係ありません。自分でコストをかけない限り、学費はかかりません。
学習の方法は独学でもかまいませんし、受講料を支払って資格予備校に通ってもかまいません。
最近だと資格予備校だけではなく、オンラインで受験対策を学習できるサービスを提供している会社があります。例えば、10万円ー20万円くらいで高レベルな受験対策の講義を受けることもできます。
独学、資格予備校、オンラインサービスの3つの学習方法のうちから、あなたの使える時間とお金に合わせて、自分でプランを組むことができます。
というわけで、なぜ毎年多くの人たちが司法書士試験を受けるかと言えば、誰でも受験できる「とっかかりの良さ」と、合格すると「法律の専門家」として、登記や裁判などの司法書士として取り扱うことができる業務を「報酬をもらって」おこなうことができるようになるからです。
まとめ
今回は、司法書士は難関資格なのに割に合わないのか?というテーマで、
という3つのお話をしました。
司法書士という資格をとっても割に合うのかどうかは、その人しだいになりますが、司法書士試験を受験するまでのコスパはとても良いと思っています。
関連記事
司法書士試験に合格するまでスクール費用が100万円かかりました
【3000時間説】司法書士の試験合格のために必要な勉強時間について考えてみた
関連記事
スタディングの司法書士試験の無料講座をまじめに受講したレビュー
資格スクエアの司法書士試験の無料体験講義をまじめに受講したレビュー
クレアールの司法書士試験の無料お試し受講をまじめに受けたレビュー
アガルートの司法書士試験講座の無料体験をまじめに受講したレビュー